8月2日に、都中国夏季研修会が中野区立明和中にて行われました。
研鑽に熱心な先生方が60名以上集まり、活気あふれる研修会となりました。
まずは、文学的文章の研究班による、主体的な読者を育むための提案として、学習ツールとしてのマンダラチャートを用いた授業案が紹介されました。

この報告は、11月に行われる埼玉大会発表の中間報告でもあります。ICTを国語の授業でどう活用するかということを出発点として取り組んだそうです。事例では一人一台端末を活用し、情報をおたがいに共有しながら読みを深めていく授業の様子が報告されました。
続いて、この報告に対する協議です。今回は、4人班をその場でつくり、自己紹介から始めました。その後、発表を聞いて感心したところ、また改善点や質問などを愛のあるダメ出しの形で協議しました。



和気あいあいとやっています。参加された校長先生からは、若い先生方の熱心さに圧倒された!との声も上がりました。
いくつかの意見を紹介します。
●多角的に読むという仕組みを意図的に演出できる。個人差があるものなので、できる生徒はマスを埋めることがゴールにならないように、書けない生徒にどういう手立てを示すかが課題。
●高校で選択制になった文学を学ぶ意義や、見方考え方を伸ばすことの大切さについてとても心強いアドバイスになった。マンダラチャートを使うときに、真ん中の観点について方向性があるべきなのか。例えば、心情・行動・人物像などの観点があるべきなのか教えてほしい。
●多角的・多様ということの定義があるとよい。生徒に書かせるときに具体的な提示があるとよい。
●マンダラアートを読みにもっていく発想がよかった。多様な読みのための材料が豊富に集まる実践で、興味深かった。単元として、このマンダラチャートをどのように扱うのか。最終的にはどのように評価したのかが知りたい。
最後には、東京女子体育大学教授 渋谷正宏先生に、多角的な読みと文学の授業の必要性、主体的な学習に取り組む態度についてご講演・ご講評いただきました。文学的文章を授業で扱うことの意義が揺らいでいる中、力強く背中を押していただいたように思います。こういったお話しを聴くと、やる気が奮い立ちますよね。講演の最後には、国語科の教師としてどうやって「主体的な学習に取り組む態度」を評価していったらいいか、という大きな宿題も出していただきました。みなさんで取り組んでいくべき大きな宿題ですね。長期休業を利用してリフレッシュしながら、また新学期に向けてアイデアを練っていきましょう。
@中野区立明和中学校-300x158.png)
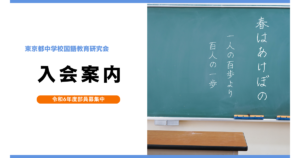


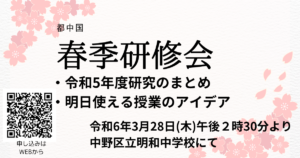
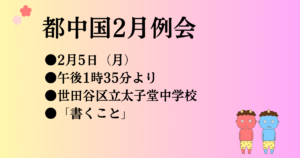

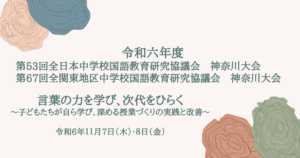
コメント