前回、古典に「読みとり」は必要か、という題で研究を進めました。そのことに関するご意見は、おおむね賛成というものでした。(総論賛成、部分で心配という声もありました。)ご意見を紹介します。
とてもおもしろいと思いました。学習指導要領の知識・技能のアでは「古典に親しむ」と書かれているので、読み取りの簡略化は可能だと思います。しかし、2年生のイの「作品を読むことを通して」や3年生のイの「引用を通して」を可能にするためには、読み取らせる場面も必要なのではないでしょうか。そして、私たちが「読み取らせるのが難しい」と感じているのは、現代語訳を読ませても、生徒が文化的背景を理解していないために、古典のおもしろさや深みを味わえない。」という課題があるのでしょうか。何よりも、高校古典や他県の高校入試のことを考えると、読めるようにしたい、という思いもあります。
妥当だと思う。内容の把握は現代語訳や注を利用し、その上で言語活動を展開するのがよいのではないか。
必要なことだと思います。必要最低限のことだけを行い、古典に親しむことを重視したいです。
面白い試みと思います。高校の授業のギャップが心配です。
中学校では、文法事項等を指導する時間をできるだけ削った方が良いという部分は賛成です。ただ、「話すこと・聞くこと」や「書くこと」との親和性の高さは、アウトプットの部分であり、そこに至るまでの指導をどうするかはかなり工夫が必要だと思います。
みなさん、「読みとる」ことに課題を感じておられることがよく分かりました。
「高校古典」「他県の高校入試」「高校の授業(と)のギャップ」(括弧内筆者追加)という言葉がありました。これはきっとみなさん気にするところとなるでしょう。
研究を進めていく上で大切なのは「定義」です。「立ち位置」と言い換えてもいいかもしれません。この研究において、「高校国語」に関する立ち位置は次のように考えることにしましょう。
生徒によって今後学ぶであろう「古典」は大きく異なります。高校の古典は、必履修の「言語文化」2単位と、選択科目の「古典探求」4単位に組み込まれています。高1で学ぶ言語文化には、古典から近代の文章までが採り上げられています。「方丈記」と「羅生門」が同じ教科書に入っているわけですね。 高校の教科書は同じ教科書会社でも、難易度に差をつけて複数発行しています。目次を見れば一目瞭然、教科書の難易度によって入っている古典教材の量が段違いです。高校は、自校の教育課題に合わせて、教科書を選択するわけです。基本的に「言語文化」は2単位ですから、週に2時間の授業で設計されています。しかし難易度の高い教科書を選択した場合は、3単位で授業を行っています。当然授業の中身も大幅に異なっています。
さらに大学入試も見すえて、2年生で「古典探求」を3単位設定する学校もあります。「古典探求」は基本4単位の選択科目ですが、3年生で設定すると入試対応が遅れるために2年生で設定し、他教科とのバランスも考慮して4単位から3単位にしているのでしょう。場合によっては、2年生から3年生への選択必修にしてみたり、まったくの選択科目にしてみたりと、高校によってまったく異なります。
したがって中学時点で何を身に付ければよいかというのは、上限を考えるのではなく、ミニマムな部分を考えるべきです。先に述べたとおり、生徒によって今後学ぶであろう「古典」は大きく異なるからです。高校での学習のために何を身に付けておくか、ではなく、中学生として身に付けさせたい力とは何か、という視点で考えを進めるべきです。 そのうえで、生徒の興味・関心に応じて、深いところまで探求できる授業の仕組みを考えていきたいと思います。
研究の方針が明らかになりました。
●中学生として身に付けさせたい古典の力とは何か。
●生徒の興味・関心に応じて探求できる古典の授業とはどんなものか。
方針が明らかになったところで、今回はここまでにします。次回までのアンケートへの協力をお願いします。ずばり、「身に付けさせたい古典の力とは何か。ご自身で実践している内容を教えてください。」というものです。いつものように、下のQRコードからご回答ください。できるだけ多くの回答を集めたいです。このプロジェクトをおもしろいと思って参加していただける人が多ければ多いほどいいものになります。
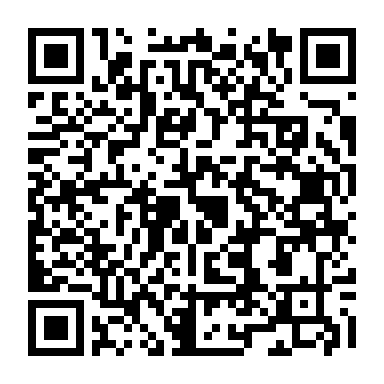
古典再定義プロジェクトは、だいたい2週間ごとに更新をします。都中国部員以外のみなさまも、参加をお待ちしています。



コメント